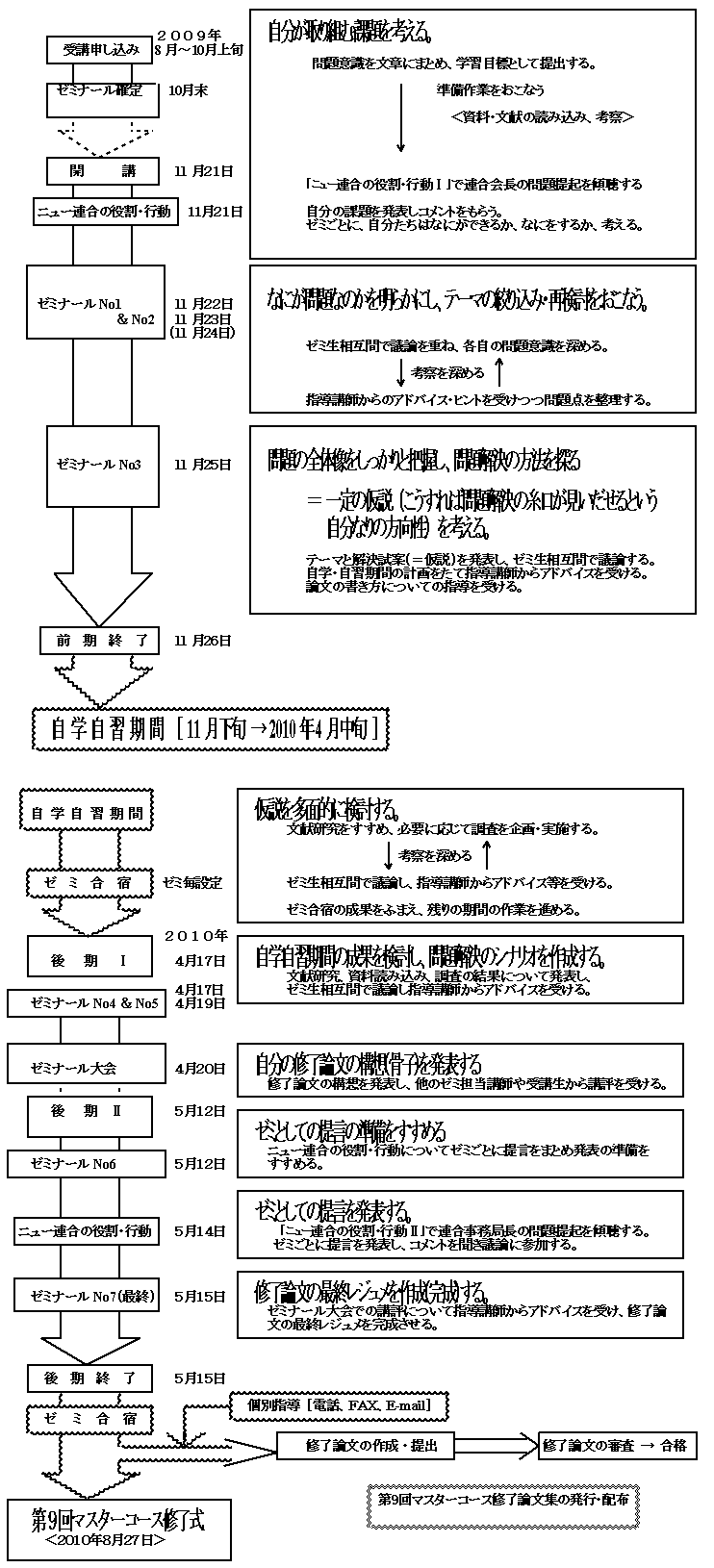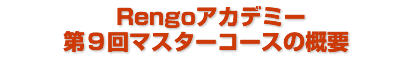目次
- マスターコースのアウトライン
- 授業プログラム
前期、 後期 I、 後期 II - 講義領域・分野と講義科目・時間一覧
- 講義科目・講師一覧
- ゼミナールの紹介
- ゼミナールの進行と課題
1.マスターコースのアウトライン
 社団法人教育文化協会は、連合運動の発展に資する労働者教育の全体像を構想し、その第一歩として、連合結成10周年を機に、2001年5月、連合運動の次代を担うリーダーの育成を目的に、「Rengoアカデミー・マスターコース」を開講しました。これまでに202名が受講し、修了生は現在、それぞれの立場から連合運動の一翼を担い、活躍しています。
社団法人教育文化協会は、連合運動の発展に資する労働者教育の全体像を構想し、その第一歩として、連合結成10周年を機に、2001年5月、連合運動の次代を担うリーダーの育成を目的に、「Rengoアカデミー・マスターコース」を開講しました。これまでに202名が受講し、修了生は現在、それぞれの立場から連合運動の一翼を担い、活躍しています。
第9回目の今年は、過去8回取り組んだ経験・反省をふまえ、引き続き(受講生出身組織の)送り出しやすさと(受講生本人の)参加しやすさを基本に、[1]講義、ゼミナールの時間配分の適正化、[2]講義内容を考慮した科目の整理統合、[3]ゼミナール大会や特別講義など特別プログラムの充実に努め、前・後期の合宿日程の効果的編成を心がけました。
第9回マスターコース・プログラムのアウトラインは以下のとおりです。会員組織(連合構成組織および加盟組合を含む)、地方連合会からのご参加を期待しています。
視点
◎マスターコースでは、人間・歴史・世界・「場」からのアプローチを重視し、受講者の分析力・構想力の醸成をはかり、問題発見と問題解決の能力向上をめざします。
注:「場」とは、問題を発見しその解決をはかるときの自分のスタンドポイントのこと。
◎合宿教育をとおして受講生と講師の「人間としての結びつき」を深めます。
年間スケジュール
◎マスターコースは、合宿教育期間と自学・自習期間を組み合わせ1年間で修了します。
◎集中合宿は、前期、後期の2期制です。
前期は、2009年11月21日(土)~11月26日(木)の6日間
(11月26日ILECサロン終了後あるいは翌日朝食後解散)
後期は、I と II に分けて、
後期 I は2010年4月17日(土)~4月20日(火)の4日間、
後期 II は2010年5月12日(水)~5月15日(土)の4日間、です。
◎前期終了後から後期開講までの間と後期Ⅱ終了後から修了論文完成までの間が、自学・自習の期間となります。この期間にはそれぞれ、必修のゼミ合宿を配置しています。
ゼミ合宿では、自学・自習期間の成果を発表し、ゼミナール担当講師からアドバイスを受け、後期のゼミへ、さらには修了論文へとつなげていきます。
修了論文については随時、担当講師からメール等で個別指導を受けることができます。
◎受講生は、2010年6月30日(水)までに修了論文を提出し、審査に合格して8月27日(金)の修了式をむかえ、1年間のプログラムを修了します。
授業と講師陣
◎前期、後期の合宿教育では、授業は講義とゼミナールを併用しておこないます。
◎講師陣は、それぞれの分野の第一人者、若手研究者を中心に、連合の会長(Rengoアカデミー校長)や事務局長、副事務局長も加わり、総勢24名です。 このほか、特別講義も予定しています。
講義
◎講義は、講師からの問題提起、GW(グループワーク)、発表などを組み入れておこないます。
◎講義科目は、特別講義などの特別プログラムも含めて24科目です。
講義時間は、授業60~70分と休憩10分のサイクルが基本ですが、講師の都合によっては、多少、授業時間が長くなったり短くなったりすることがあります。
◎前期の最初の講義、「ニュー連合の役割・行動Ⅰ-労働運動における自己の役割-」では、連合会長からの問題提起、質疑応答のあと、受講生は各自の課題を発表し、会長がコメントします。また、自分たちは何ができるのか、何をするか、ゼミごとに考えます。
◎後期の最後の講義、「ニュー連合の役割・行動Ⅱ-労働運動における自己の役割-」では、連合事務局長の問題提起、質疑応答の後、ゼミごとに「提言」を発表し事務局長がコメントします。
そして、全体でディスカッションをおこないます。
ゼミナール
◎受講生は、受講申込みの際に、「考察を深めたい課題」を提出します。この課題にもとづいて、受講生は5つのゼミナールのなかから希望するゼミを選択します。
◎ゼミナールは、1回2時間30分(休憩含む)、前期3回、後期4回(後期Ⅰ:2回、後期Ⅱ:2回)の計6回おこないます。
◎ゼミナールは、5~6名で編成し、担当講師の指導やゼミ生との議論をとおして、各自の課題を修了論文に仕上げます。
◎ゼミナール大会(後期Ⅰ最終日)では、受講生が修了論文の構想あるいは骨子を発表し、ほかのゼミ担当講師から講評を受けます。後期Ⅱのゼミでは、その講評も含めゼミ担当講師から指導を受ける。
募集・受講料
◎募集人員は30名。募集期間は、2009年8月3日(月)~10月5日(月)。
◎受講料は前・後期あわせて20万円。ただし、前期と後期とで各10万円ずつ分割納入することもできます。また、受講料の割引き措置もあります。
合宿期間中の運営
◎合宿生活は、受講生が実行委員会をつくり運営します。
合宿期間中、連合会長、事務局長、教育文化協会理事長との交流、懇談の場を設定しています。
修了
◎修了要件は、前・後期を受講し、修了論文を提出し審査に合格することです。
修了者には、修了証を授与します。
2.授業プログラム
前期 [2009年11月21日(土)~11月26日(木)]
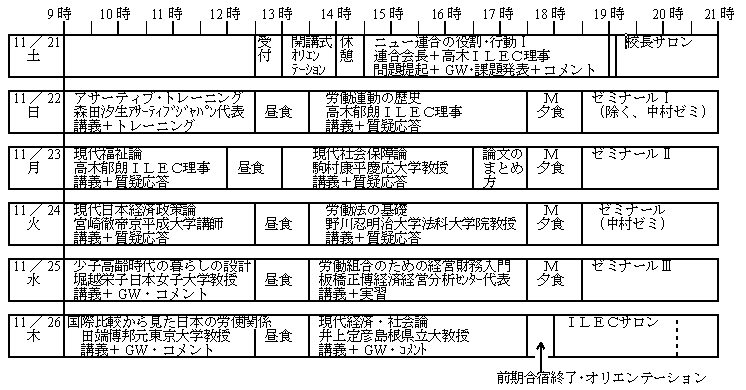
[備考]
[1] 開講式直後に、合宿プログラムや合宿生活全般についてオリエンテーションを行う。
[2] 講義は、トレーニングや質疑応答、GW(グループワーク)も含め、授業時間60~70分と休憩時間10分のサイクルを基本とするが、講義の都合上、多少、講義時間が延びることもある。
[3]午後の講義終了後、実行委員会のミーティング(M)を行う。
[4] 「ニュー連合の役割・行動I」では、連合会長の問題提起、GWと質疑応答のあと、自己の課題を発表しコメントをもらう。
[5] GW(グループワーク)・コメントでは、講師の出された課題について各班(ゼミ単位)ごとに議論(15分程度)し、
結論を発表し(各3~4分)、講師からコメントをもらう。
[6] ゼミナールの運営は担当講師一任。
[7] 校長サロン、ILEC(教育文化協会)サロンは、受講生との懇親および受講生相互の交流を目的に開催する。
[8] 前期終了後に、後期Iまでの「自学・自習期間」の過ごし方などについてオリエンテーションを行う。
[9] 受講生は、11月26日ILECサロン終了後あるいは翌朝、朝食後に解散する。
後 期 I [2010年4月17日(土)~4月20日(火)]
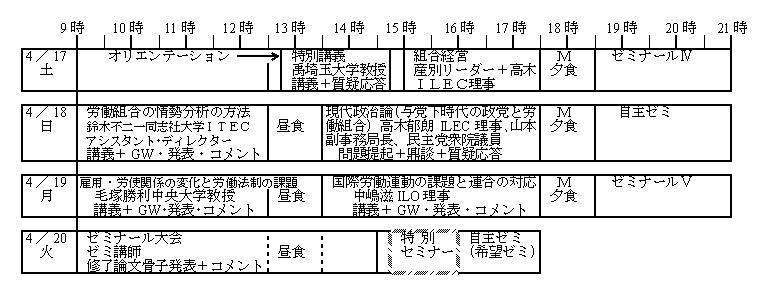
後期 II [2010年5月12日(水)~5月15日(土)]
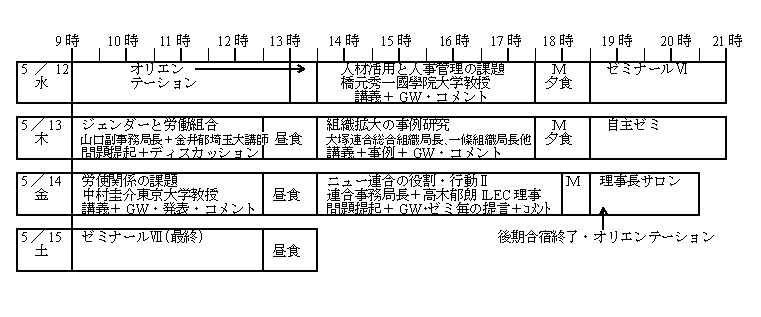 [備考]
[備考]
[1] 後期Iスタート時に、修了論文の作成などについてオリエンテーションを行う。
[2]「ゼミナール大会」では、受講生はひとりずつ修了論文の構想・骨子について発表し、他のゼミ担当講師から講評を受ける。
[3]「特別セミナー」では、労働者自主福祉活動に取り組んでいる中央労福協、ろうきん、全労済の全体像を簡潔に紹介する。
[4] 「ニュー連合の役割・行動II」では、ゼミ毎に討論した内容を発表し、連合事務局長からコメントをもらい、全体で論議する。
3.講義領域・分野と講義科目・時間一覧
 講義科目は、政策-組織-基礎の3領域、総合戦略-経済産業政策-社会労働政策-組織強化・拡大-組織運営-人間と組織-経済・政治と労働の7分野から編成しています。
講義科目は、政策-組織-基礎の3領域、総合戦略-経済産業政策-社会労働政策-組織強化・拡大-組織運営-人間と組織-経済・政治と労働の7分野から編成しています。
講義は、連合の戦略的方向性・課題を大づかみに理解し、連合の一員としての自分の役割・課題を確認することからスタートし、基礎から応用へ、順次ステップアップできるように科目を配置しています。本年度は、これまでの運営経験と受講生のアンケート結果を参照し、新たに2科目開講しますが、講義時間の見直しと時間配分の適正化などを行い、昨年と同様の講義時間数に収めることが出来ました。このほか、正規のプログラムに加えて、「特別セミナー」の開催も予定しています。
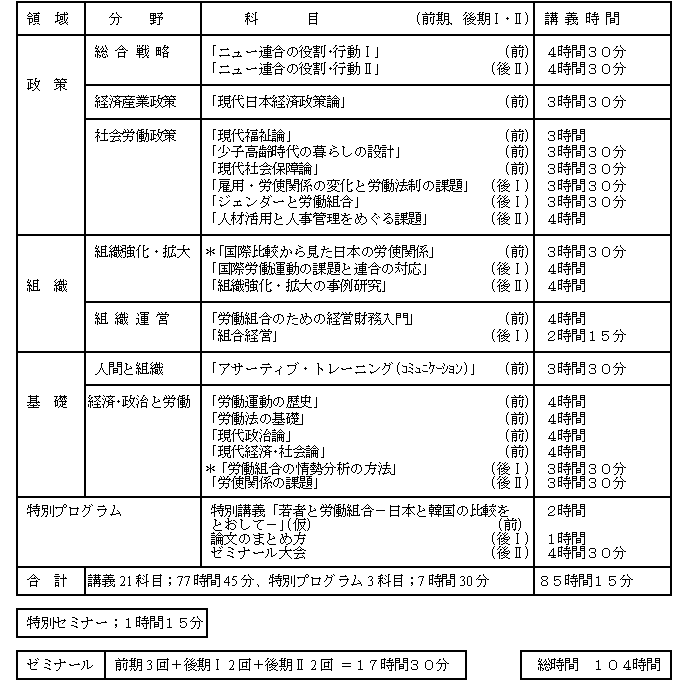
4.講義科目・講師一覧(調整中含む)
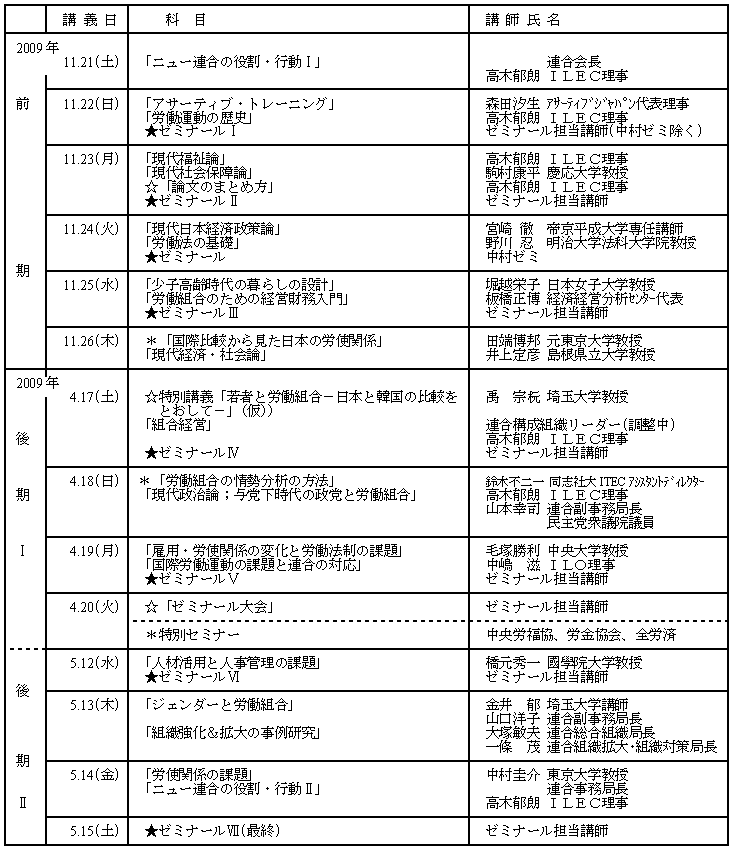
5.ゼミナールの紹介
| 廣瀬ゼミ | テーマ:人間・地域と労働組合 | 講師:廣瀬真理子 東海大学教養部教授 |
|---|---|---|
| 目的 |
|
|
| 課題(キーワード) | 少子・高齢社会/家族規模の縮小化/家族形態の変化/医療改革/所得保障改革/契約福祉/自立支援/利用者本位/福祉多元主義/地域福祉と労働組合/EUの社会保障と労働組合/ワークライフバランス/フレキシキュリティ/ソーシャルインクルージョン | |
| 高木ゼミ | テーマ:経済・産業と労働組合 | 講師:高木郁朗 山口福祉文化大学教授・ILEC理事 |
|---|---|---|
| 目的 |
|
|
| 課題(キーワード) | 産業構造の変化/社会構造の変化/グローバリゼーション/FTA・EPA/技術革新/市場万能主義/CSR(企業の社会的責任)/ワークフェア/ディーセントワーク(人間的労働)/福祉ミックス/持続的経済成長/三者協議制度/SRI(社会的責任投資) | |
| 中村ゼミ | テーマ:経済・産業と労働組合 | 講師:中村圭介 東京大学社会科学研究所教授 |
|---|---|---|
| 目的 |
|
|
| 課題(キーワード) | 時間外労働/成果主義/非典型雇用/経営参加/労使協議/目標管理/外部人材/行政参加 | |
| 橋元ゼミ | テーマ:企業・職場と労働組合 | 講師:橋元秀一 國學院大學経済学部教授 |
|---|---|---|
| 目的 |
|
|
| 課題(キーワード) | 採用/従業員構成/非正規労働者(非典型雇用)/配置/教育訓練/賃金/成果主義/人事考課/労働時間/残業協定/労使協議/経営参加/組合組織構造/組合役員 | |
| 毛塚ゼミ | テーマ:労働法と労働組合 | 講師:毛塚勝利 中央大学法学部教授 |
|---|---|---|
| 目的 | 次のような課題のなかから参加者の関心にそった問題を検討することにしたい。
|
|
| 課題(キーワード) | WLB/派遣労働/パート労働/均等待遇/企業分割/営業譲渡/投資ファンド/M&A/雇用差別/間接差別/障害者雇用/ハラスメント/メンタルヘルス/労働審判/労働契約法/変更解約告知/労働者代表(従業員代表)制度 | |
6.ゼミナールの進行と課題