■第3回(5/13)■
課題と取り組み(1)労働時間を中心としたワークルールの取り組み
1.はじめに
(1)5つの設問
連合の新谷です。私は連合で、労働条件の中でも賃金を除く労働時間、雇用のセーフティネット、安全衛生などに関わる法律の制定や改正に取り組んでいます。
今日のテーマは労働時間を中心としたワークルールについてです。皆さんがこれから社会人になって働くときに、労働時間は重要な労働条件の1つになってきますが、そのワークルールはどのようになっているのか、労働条件は誰が作るのかについてお話しします。なお、学生の皆さんには雇用関係についての説明はなかなか難しいので、模擬的に労働者A君はどうするかという資料を作りました。それぞれの内容について正しいと思ったら○を、そうでなければ×を、どちらともとれると思ったら△をつけてください。
民間企業サラリーマンとしての生活を始める“労働者”A君はどうする
- A君は大学卒業後、大手企業B社に入社した。A君は入社式の手続きのなかで「労働契約書」というものにサインをした。会社での労働条件は、採用時にサインした時に決められていた条件がずっと適用されるし、将来、会社が労働条件を引き下げる変更をする場合には労働者一人ひとりの同意が必要であると思う。
- B社で働き始めたA君は、集合研修を終えて、配属された職場での新入社員研修に取り組んでいる。入社から4カ月になるが、もうすぐ8月。学生時代なら夏休みで遊びやバイトに忙しい時期だ。職場の先輩は年次有給休暇を使って夏休みをとるという。A君も年次有給休暇の申請をしようと思う。
- 職場や取引先での研修をこなしながら、A君はB社での仕事にも慣れ、職場の先輩や同期入社の仲間とも飲みに行く余裕も出てきた。学生時代からの彼女と就業後のデートのために奮発して高級レストランを予約した。ところが大型受注が舞い込み、職場総出で対応しなければならなくなり、課長からデートの日に残業を命じられた。大切なデートの日の残業は拒否できると思う。
- ある日、会社のイントラネットにある人事部のHPで就業規則というものを見つけた。労働条件や職場規律などを規定した会社の文書のようだ。研修先の先輩に聞くと、就業規則というのは会社が作るが、それを作成する際や変更する際には、労働組合は意見を述べることができる。しかし、労働組合が反対した場合は変更できないとのことだ。
- A君はまもなくB社にあるB労働組合の組合員になったが、会社が作る「就業規則」とは別に、労働条件などに関して労働組合と会社の合意文書である「労働協約」というものがあるそうだ。就業規則と労働協約は同じ内容が書かれているそうだが、労使対等に基づき、会社が制定する就業規則と労働協約は同じ効力を持っていると思う。
(2)日本は雇用社会
それでは、この設問の解説を含めて話をします。最初に日本の雇用の状況、労働時間の基準や規制の流れを説明し、法律で決められた労働基準と労働組合の自主的な取り組みによる労働基準の違いを説明します。そのあと、法定の労働時間の基準の具体的内容を説明します。そして、各企業での具体的な労働条件が作られるプロセスをお話しし、最後にまとめという流れで進めます。
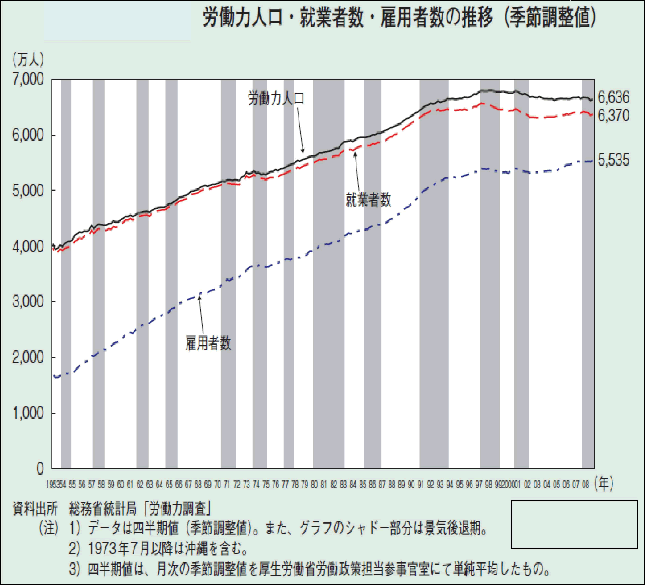
出所:労働経済白書2009
まず、日本は就業者の8割が雇用関係の下で働く雇用者ですので、「雇用社会日本」と言えます。
表-1は、総務省の統計局が行った労働力調査という調査のデータを基に作成されたもので、就労者数と雇用者数の変化を示しています。
就業者というのは、自営業、農業、林業、漁業など職業を持っている方です。そのなかに占める雇用者は、雇用関係にある、企業と労働契約を結んで働いている方の数です。この雇用者数はどんどん増えてきています。日本の人口1億3,000万人のうち、2008年では6,370万人が職業を持っていて、そのうちの5,535万人が雇用者です。日本では職業を持っている人の実に87%が雇用関係のもとで働いています。
この数字は非常に高く、先進工業国はだいたい似たような数字になっています。日本は雇用関係が中心の社会です。ですから日本の社会の安定のためには、この雇用関係の安定を図る必要があります。労働者が安定的な生活を送れるということが重要であり、そういう前提のなかでも重要な要素である、労働時間の話をしたいと思います。
2.日本の労働時間規制の流れ
(1)明治期の状況
現在の話をする前に、振りかえりのために資料を作りました。表-2は明治期の労働時間がどうだったのかという一つの例です。当時の日本政府の農商務省が、全国で働いている人の労働条件を調査してまとめた『職工事情』という冊子があります。
当時の日本の輸出品の第1品目である生糸を扱う製糸工場での女性労働者、女工の労働条件を調べたものです。まず、朝4時に起床します。6時に朝食を15分ですませ、10時30分にまた15分で昼食、15時に15分間の休憩をとり、終業が19時30分です。実に1日の総労働時間が14時間15分という数字です。
表-2 工場法以前の労働時間の例(製糸工場) 『職工事情』1903年農商務省調査より
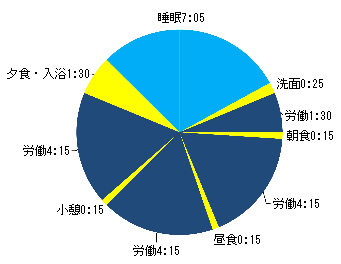
これは長野県の器械製糸工場の例で、県内労働者32,000人、うち66%が20歳未満の労働者です。さらに、このうちの18%が14歳未満の労働者です。いまでは考えられない状況ですが、いわゆる児童労働が行われていたということになります。
こういう実態に対し、当時の日本政府は労働規制を考え、最初にできた法律が「工場法」です。この法律は、1911年に成立し、施行は5年後という、長い期間をおいて施行されました。この法律による就業年齢は12歳以上です。最長労働時間は12時間で、ただし15歳未満の男子と女性に限るという規制です。休日は月2回、これも15歳未満の男子と女性に限り、かつ深夜業についても15歳未満の男子と女性を対象に禁止としています。これが日本で最初にできた労働者保護法の中身です。なお、児童労働にはなりますが、この法律の施行前から雇っていた10歳以上の労働者については、軽易な業務のみ就いてよいとされました
(2)最低限の法規制とそれを上回る規制
次に、戦後にできた労働者を保護するための法規制についてお話します。これからお話しする領域は2つあります。1つは、労働者保護のため、直接、国が介入する領域です。本来、労働契約は、個人と使用者間の契約です。それに国家が介入して、最低限の労働条件で労働者を保護するために、法律で規制をかけます。その法律が「労働基準法(以下労基法と略記)」、「労働安全衛生法」「最低賃金法」などです。私的な契約関係に国家が介入して労働者の保護を図る目的の法律で、最低限の労働条件を法律が直接決める領域です。
もう1つ、最低基準を上回ってはいるが、労働者と使用者が労働契約を結ぶときや、あるいは解雇のように労働契約を解消するときなどに、法律が入ってくる領域があります。いわゆる契約自由の世界に法律が入ってきます。この2つの領域が重なっている会社と、離れている会社ではどちらが良いでしょうか。当然ですが、重なってしまったら、国で決めている最低労働条件で働くということになります。重なっている部分が離れていくほど、労働条件が上がっていくことになります。なお、会社によって重なり具合が違い、その違いはなぜあるのか、重ならない部分はどうやって決まるのかは後ほどお話しします。
(3)労働時間規制の現状
まず、法による労働時間の最低基準の部分をお話しします。労基法の第32条では、1日と1週間の労働時間の上限を決めています。「使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働をさせてはならない」「休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない」とあり、明治期の労働条件とはずいぶん違います。労基法が成立した1947年は、週は48時間でしたが、法律改正をしながら50年かけて1997年には40時間まで短縮しました。現在は週40時間、1日8時間が基準です。1日8時間働くと、40時間に到達するのは5日間ですから、月曜日から始まると金曜日までです。また、1週40時間をクリアするということであれば1日は8時間でなくてもいいので、7時間ずつで金曜日まで働くと35時間です。法定時間を超えないということになると、土曜日に残りの5時間を就業させることは可能です。
休憩時間も法規制があり、使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超えたら1時間の休憩時間を一斉に与えなければなりません。
休日の規制は、毎週1回の休日、それが無理な場合には、4週間を通じて4日以上という規定になっています。
(4)残業を適法とする36協定(サブロク協定)
次は、ある条件を満たしたとき、法定の労働時間を超えて働かせることができる、日本特有の法律体系についてお話します。労基法第36条には、「過半数の労働組合がある場合は労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定をした場合、40時間を超えて労働をさせることができる」と書かれています。これは労使協定があれば1日8時間、週40時間の規制を超えることができるという規定で、第36条の規定から「サブロク協定」と言っています。この労使協定がないと法定労働時間を超えて働かせると、労基法32条違反ということになります。
労基法は、最低限の条件を国が規制し、それを破ったときは刑罰をもって対処されます。国家が刑事罰を科して労基法に違反しないようにしています。また、これに関わって労働基準監督署があります。この監督署は司法警察権限を持っています。労基法違反があれば、監督官が事業所に立ち入り調査をする権限もあり、違反があれば地方検察庁に書類送検し、刑事罰が科されます。ただし、こうした違反による罰則は、労使協定を結ぶことにより科されなくなります。この罰を免ずるこのような労使協定を「免罰条項」、「免罰協定」といいます。
では、この労使協定があれば何時間でも働かせられるかというと、1週間は15時間、1年間は360時間までという上限時間が決まっています。しかし、これには法的な拘束力がありません。一方、臨時的に残業させなければいけない場合には、その理由をつけて別途協定を結ぶと、何時間でも働かせることができます。とてつもない残業時間の協定が監督署で受理されています。拘束力がないために受理されてしまうわけですが、このような実態は過労死にもつながっています。こうした免罰条項は、労働時間法制のなかで一番の問題と言えます。36条の協定によって、法による労働時間規制が実態的に緩められていることは問題で、ILO(国際労働機関)の第1号条約を批准できない理由がここにあります。この第1号条約では、労働時間は1日8時間、週48時間と規定していて、先進国のなかでは日本とアメリカがこの条約を批准できていません。ちなみに日本は労働時間の関係のILO条約は1本も批准できていません。
次に、36協定を結ぶ際の過半数代表はどうやって選ぶかということですが、その事業場で過半数の労働者を組織する労働組合がある場合は労働組合の代表が、ない場合には労働者の代表を選挙などで選びます。表-3は、労基法で定められた、第36条の協定以外の労使協定の一例です。たとえば第18条「強制貯蓄」というのがあります。給料から強制的に貯蓄させることは禁止されていますが、それを可能とするには労使協定を結ぶということになります。これらはすべて過半数代表者との協定で行えるものです。
表-3 過半数を代表する者との法に基づく労使協定
過半数労働組合に関する労基法の規定
| 条 文 | 内 容 |
|---|---|
| 第18条(強制貯蓄) | 社内預金協定 |
| 第24条(賃金の支払) | 賃金控除協定 |
| 第32条の2(一カ月単位の変形労働時間) | 一カ月単位の変形労働時間制に関する協定 |
| 第32条の3(フレックスタイム制) | フレックスタイム制に関する協定 |
| 第32条の4(一年単位の変形労働時間) | 一年単位の変形労働時間制に関する協定 |
| 第32条の5(一週間単位の非定型的変形労働時間) | 一週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定 |
| 第34条(休憩) | 休憩の一斉付与の例外協定 |
| 第36条 (時間外及び休日の労働) | 時間外休日協定 |
| 第39条の2 (事業場外のみなし労働) | 事業場外のみなし労働の協定 |
| 第38条の3(専門業務型裁量労働) | 専門業務型裁量労働に関する協定 |
| 第38条の4(企画業務型裁量労働) | 過半数労働組合による労使委員会の委員の指名 |
| 第39条(年次有給休暇) | 年休の計画的付与に関する協定 |
| 第90条(就業規則の作成) | 就業規則作成・変更時の意見書 |
(5)年次有給休暇と労働時間の柔軟化
労働時間に関する労働条件のなかでも重要な年次有給休暇も、法律で最低限の基準が決まっています。労基法第39条では、雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合は、継続、または分割した10労働日の有給休暇を与えなければな。「設問2」のA君のケースは、もうすぐ4カ月になるというケースでした。職場の先輩は、勤務が6カ月以上であれば、10日与えられます。しかし、A君の場合は4カ月しか経っていないので、取ろうと思っても休暇は与えられません。ですから、最低限の労働条件ということであれば、この設問の答えは×です。一方、「就業規則」や「労働協約」などの規定によっては、設問の答えは変わってきます。労基法上は、入社6ヵ月以内は年休を与えなくてもよいことになっていまが、労基法を上回る条件を決めている会社があります。大手企業では、入社から1ヵ月で年休を与えるケースが多くあります。法定どおりの場合、6年半経つと20日となりますが、実際には、法を上回って例えば25日としているところも多くあります。
【法定の年次有給休暇の付与日数】
| 勤続年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
また、労基法には、1日8時間、週40時間を柔軟化するための労働時間制度の特則があります。変形労働時間制やフレックスタイム、みなし労働時間制などの仕組みです。今年の夏は電力不足が予想されており、いかにピークの電力使用量をカットするかが重要となっていますが、そのために昼間と夜間を入れ替え、労働時間を夜にシフトするという動きがあります。あるいは労働日を変更して、土曜・日曜に働いて、木曜日と金曜日に休むという会社などが出てきています。このような1日8時間、週40時間を柔軟化する労働時間の特則が労基法にはあり、電力不足が予想される今年の夏は、こうした対応はたくさんでてくると思われます。
(6)総労働時間の傾向
次に日本の総労働時間の傾向についてお話しします。日本の労働時間は、1980年代から先進国のなかで一番長かったのです。ドイツが一番短いのですが、ヨーロッパは総じて短いです。日本はだんだん短縮されて、やっとアメリカ並みになってきました。
一人当たり平均年間総実労働時間(就業者)
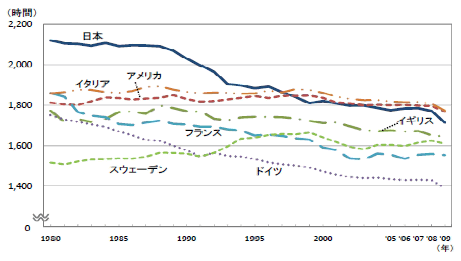
なぜ短縮できたのかということですが、1986年に大きな転機がありました。この頃の日本は高度成長期で、日本のGDPはアメリカのGDPの7割近くまで増えました。ところがそのとき非常に労働時間が長かったため、先進諸国から「日本は働きすぎだ」という批判を浴びて、是正するために国策として労働時間の短縮を進めました。「前川レポート」という重要な報告書があり、これは当時の中曽根総理大臣に出された提言で、労働時間を短縮し、週休二日制を実施しようという提案です。日本はこれを86年の東京サミットで、諸外国に対する国際公約としました。そして最初に行ったのが労基法の改正で、1週間の労働時間を48時間から40時間に短縮し公約を果たしました。ところが最近の年間総労働時間の推移を見てみると、この4、5年で労働時間が減ってきています。この背景には、顕著な法改正があったわけではなく、中身を分析してみると、パートタイム労働者などの非正規労働者が増えて、労働時間の短い労働者の比率が高まっていることがあります。ですから、一人あたりの平均値をとると、総労働時間が減ってくるということです。いわゆる正社員の労働時間はあまり減っていないのですが、非正規労働者の構成が変わってきているため、労働時間の平均値をとると下がってきています。
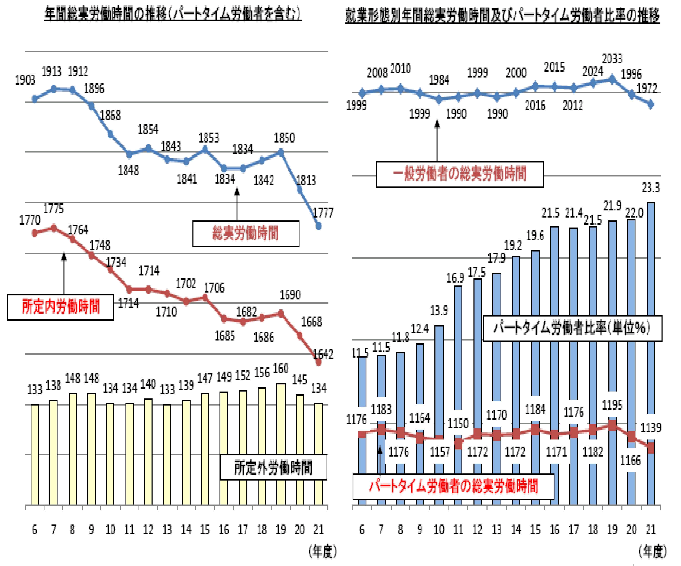
出所:厚生労働省「多様な形態による正社員に関する研究会」
ちなみに、総労働時間の短縮につながる年休の取得率が一番高かったのは90年代で、これもどんどん下がっていて現在5割を切っています。権利としての休暇があっても労働者は取りきれていないのが現状です。
また、日本では、長時間働く人と短時間の人で二極分化しています。週60時間以上働く人が1割います。特に30代の男性の5人に1人は週60時間以上働いています。過労死の問題は、年代でいうと30代の男性に顕著です。1カ月で80時間以上残業する人も10人に1人いるという実態です。一方、週の労働時間が35時間未満の人が非常に増えていて、現在、労働時間の二極分化が著しく進んでいます。
(7)「不払い残業」「名ばかり管理職」「過労死」の問題
労働時間の問題の一つに不払い残業があります。法定労働時間を超えた残業には割増賃金を払う必要があり、1時間に対して平日では最低限25%、休日は35%の割増となっています。不払い残業とは、残業をしても残業代が払われないというケースです。
労働基準監督署は事業所への立ち入り調査を実施して不払い残業を摘発しており、是正企業は2009年度では1,200社、是正により支払われた金額は116億円にものぼっています。
もう1つは「名ばかり管理職」の問題です。この事例としては「日本マクドナルド事件」がありますが、マクドナルドの店長は管理職ということで残業代は払われていませんでした。実は労基法の1日8時間、週40時間の労働時間規制には適用除外があり、管理監督者は適用除外とされています。では、誰が管理監督者なのかということになりますが、企業が勝手に肩書をつけてしまうケースもあります。たとえば、私の知っている企業では、営業所の15人のうち13人が課長以上というケースもありました。管理者には残業代を払わなくていいということで、そのような会社が存在します。適用除外の対象となる管理監督者の基準が法的に決められていて、肩書などに関係なく、会社経営者と一体的な立場にあり、職務や賃金面で一般の労働者に比べ高い待遇を受けている人というものです。
さらには、労働時間の問題として、過労死の問題があります。「過労死」という言葉があるのは日本だけです。働きすぎによる病気には、脳や心臓系の疾患と、メンタル、精神面で鬱になってしまうものなどがあります。これらが労働災害として認定される件数は毎年300件ぐらいあり、そのうち亡くなる方が100人から150人で、本当に忌々しき問題です。過労死や自殺も含め、きちんと防止をしなければいけません。
連合は、現在「年間総実労働時間1,800時間の実現」をめざす運動をしています。この1800時間モデルは、1日の労働時間は7時間半、所定労働日数を240日、休暇を最低20日間、最高25日以上、時間外や残業時間を年間に150時間前後、これらによって、1年間で1,800時間とするように運動を進めています。
3.労使の自主的な取り組み:最低限を上回る労働条件の獲得に向けて
(1)ワーク・ライフ・バランスへの取り組み
皆さんが仕事に就いたとき、自分の人生は仕事だけではないと考えるときが必ず来ます。家族、あるいは地域との絆を大切にした働き方とはどんな働き方か考える、そうした気付きが大切で、それが仕事と生活のバランスをはかることにつながります。
法改正だけではなく、こうしたワーク・ライフ・バランスを進めている主体の一つに、私の出身である電機連合の運動がありますので、ご紹介したいと思います。
労働組合は、日本では企業ごとが一般的であり、たとえば、パナソニックにはパナソニックの労働組合、日立には日立の労働組合、三菱には三菱の労働組合があります。そういう産業ごとの労働組合が集まった連合会を産業別労働組合といい、電機産業では電機連合といいます。ちなみに電機産業だけではなく、自動車や鉄鋼、流通関係、スーパーなどそれぞれに産業別の労働組合があり、そこに加盟する労働組合が一緒に労働条件の産業横断的な引き上げを目指しています。
電機連合では、ワーク・ライフ・バランスの取り組みとして、電機産業で働く労働者にアンケートをとり、起床・就寝・出社・退社時間を聞きました。その結果、非常に就寝時間が遅いことがわかりました。たとえば男性30~34歳では、朝6時39分に起床、24時14分に就寝、帰宅が21時30分ですから、家に帰ってから寝るまでに4時間しかありません。特にエンジニアは21時25分に帰宅、24時23分に就寝、6時43分に起床という結果ですから、自分や家族との時間がほとんどありません。
また、仕事と生活の調和に対する満足度の調査もやりました。1ヵ月の残業時間ごとの分析では、1ヵ月の残業が40時間を超えると「満足している」が「満足していない」と逆転をすることがわかってきました。一方、残業時間が増えるとワーク・ライフ・バランスの満足度は落ちていきますが、残業時間が長くても仕事のやりがいは下がっておらず、ここが日本の労働者の問題ともいえます。仕事が面白くて仕方がない、仕事が面白いから帰らないのです。いま、働く人のワーク・ライフ・バランスへの気付きにつながる取り組みが労働組合の重要な課題となっています。
(2)「労働契約」・「就業規則」・「労働協約」 の関係
次に、法律を上回る労働条件は誰が作るのかということに触れます。
実は、設問の答えは△のところもあるのですが、ほとんどが×です。設問1ですが、会社に入ったとき、労働条件などを書いた労働契約書にサインをします。その後に労働条件の変更、たとえば「1日7時間30分だったのを8時間に戻してくれ」、「国民の祝日がある週は、土曜日を出勤にしてくれ」などと言われたとします。契約書にサインをした時点での条件で合意をしたわけですから、特に不利益に変更するのであれば本当は合意をとらないと契約の世界ではおかしいことになります。ところが、就業規則を含めた労働条件決定システムでは、労働条件を下げる場合も含めて、個々人の合意は原則として必要ないのです。したがって設問1の答えは×です。次に設問3ですが、大切なデートの日に残業命令があったときに拒否できるかどうかですが、この答えも×です。これも36条の労使協定があって、残業を命じることができるとなっていればデートだからと言って拒否はできません。ですから、基本的には働けといわれたら働かざるをえません。もっとも熱が39度も出ている、家の子どもが熱を出していて帰らなければいけないなど、そういう事情がある場合はどうするかという問題はありますが、基本的にはデートぐらいの理由では残業は拒否できません。次に設問4ですが、労働組合が反対すると就業規則は変更できないか、これは×です。設問5の就業規則と労働協約は同じ効力を持っているか、これも×です。
そこで、改めて企業毎の具体的な労働条件はどのように決まっているのかということを説明します。
まず、会社・使用者と労働者は1人ずつ契約を結びます。個別に契約を結ぶわけですから、その労働者の数だけ「労働契約」があるわけです。会社は、その契約が5人くらいなら一人ずつ作ることもできるのですが、それが千人、1万人というような企業規模になってくると、個別契約の管理は負担になり、そのため、会社は「就業規則」という統一ルールを作ります。この統一ルールである就業規則が一人ずつの契約の中身を基本的には規制します。就業規則には効力が2つあって、最高裁で確定したものですが、一つめは、その統一ルールの内容が合理的であれば、就業規則で決められている内容を労働者が知らなくても、1人1人の契約の中身になるという効力です。そして、注目すべきは二つめの効力です。その統一ルールの変更が合理的なものであれば、同意しないことを理由として労働者がその適用を拒否することはできないというものです。このルールは、一般的な契約の世界では考えられないものです。これらの最高裁判例は労働契約法という法律になっています。
ところで、設問4に、労働組合が変更に反対したらどうなるかという問題があります。就業規則は労基法で作成・変更の手続きが定められていて、10人以上の労働者を使用する使用者は、必ず就業規則を作り労働基準監督署に届け出ることになっています。変更する場合は、その事業所に過半数労働組合があれば意見を聞かなければなりません。ここでポイントは法的に義務付けられているのは「労働組合の意見を聞く」ということです。労働組合として変更に反対という意見を添付しても、その就業規則の変更を防止する効果はないのです。
就業規則は意見を聞くだけなので、そこで重要となってくるのが「労働協約」です。労働協約は、使用者と労働組合が合意した内容を文書としたものです。この労働協約は就業規則より優先されます。労基法92条では、「就業規則は当該事業所について適用される労働協約に反してはならない」と規定されていて、つまり、会社が作って会社が変更できる就業規則より、労働協約のほうが、効果が上であるということです。労働契約の中身は、最終的にはこの労働協約によって決まります。もちろん労基法で定める最低基準を上回らないといけませんが。この労働協約の内容は誰が決めるのかというと、労働組合が労働条件を決める主体として関わって、労使の交渉によって決定します。
(3)最低限の労働条件(法律)は三者構成で決定
最後に、最低限の条件を定めた法律は、誰が決めるのかについて話をします。労働条件の最低限は「労基法」で決めるのですが、その決め方に関わる問題があります。
割増賃金の最低基準は、去年の4月から引き上げられ、残業が60時間を超えた場合は50パーセントの割増賃金を払うことになりました。しかし、このルールは中小企業については適用しないということになっています。中小企業のほうが労働条件は悪い場合が多く、より法規制が重要で、大企業のみの適用は、連合としては非常に不満です。
連合は、法律改正が必要な内容に関する取り組み課題を毎年決めています。たとえば、去年の4月施行の労基法については、「中小企業についても適用する」「休日の割増賃金を早期に引き上げる」「新しい考え方である休息時間(勤務間隔)規制を導入する」といった目標を掲げています。これらの目標を実現するためには法律改正が必要です。
労働に関する法律を作るプロセスは、ILOに加盟している国は共通の仕組みを作らなければ、ILO条約の基準を達成できません。この仕組みとは、「政府」、「労働側代表」(連合が担っています)、「使用者代表」(経団連や商工会議所など)の三者で構成する審議会での決定に基づくというものです。日本の場合は学識経験者がその仲立ちをします。三者構成の審議会で合意を得た内容を厚生労働大臣に答申・建議し、それをもとに政府は法律案を作り、閣議で決定し国会に送ります。国会審議が「衆議院」「参議院」で行われ法律が成立する、これが法律ができていく仕組みです。日本では、労働法制だけが、ILO条約に従ってこの三者構成主義をとっています。労基法改正も、セーフティネットに関する法律の改正も、ほぼこのような仕組みで決まっています。ですから、連合は労働関係の法制定や法改正に非常に重要な役割を担っています。
まとめに代えて
「労働」は単に苦役ではなく、個人の成長の原動力であり、働くことの喜びを育んでいくものです。日本では、職を持って働く人の8割以上が雇用関係のもとで働いています。ですから、「労働」が日本の経済と社会を発展させていく前提条件になると考えています。
皆さんには、これからどこでどんな仕事をするかを考えるときには、ぜひ労働組合のある職場を選んでいただきたいと思います。労働組合があって、労働協約を締結していて、民主的な職場環境を作っているところを選んでいただきたいと思います。
ご清聴、ありがとうございました。
以 上
| ▲ページトップへ |
