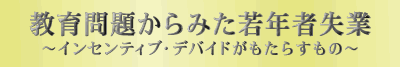| (1) |
小中学校での総学習時間の減少 |
| |
学習時間は1972年に比べると現在は約1000時間減っている。1980年代後半から1996年くらいまでは、受験競争が激しくて日本の子供達は勉強しすぎだから教える量を減らしてゆとりをもたせれば、子供達が落ちこぼれることもなくなるだろうと考えられていた。しかし、私が調べた資料では今回の学習指導要領の改訂が行われる以前から完全に勉強しすぎより勉強離れへ大きな流れが完全にシフトしていた。 |
| (2) |
家庭での学習時間の減少 |
| |
東京都が3年おきに行っている中学2年生対象の調査では、家庭での学習時間が1992年までは若干増加しているが、それ以降は減っている。全く勉強しない子供の割合も1992年以降大きく増えている。審議会がこのような傾向をもっとしっかり踏まえていれば現在の政策も少し違うものになったのではないか。審議会の記録ではこのようなデータが検討された形跡がない。 |
| (3) |
勉強をしたくない子供の増加 |
| |
神奈川県藤沢市が中学校3年生全員を対象にした勉強への意欲、集中度、自信、理解度、勉強時間の調査では、勉強をしたくない子供の割合が1995年から2000年にかけて極端に増えている。 |
| (4) |
減らない校内暴力、不登校 |
| |
教育改革のひとつの狙いである校内暴力や不登校も1992年の指導要領の変更以降もまったく減っていない。 |
| (5) |
高校中退率の増加 |
| |
1992年の改訂から子供達の意欲・興味・関心を高めようと新しい学力観で取り組んできたが少なくともそのような成果は見えてこない。 |
| (6) |
アメリカ、韓国より少ない学校以外での学習時間 |
| |
1996年時点の総務庁の調査では日本は韓国やアメリカよりも学習時間が少ない。文部省は教育改革を進める上でこのようなデータをほとんど分析していない。データを検討せずに政策が決まっていることが問題だ。 |