Rengoアカデミー・マスターコースの講義内容の一部を、講義録のかたちにまとめ、刊行しています。
Rengoアカデミー講義録
-
No.29 労働法の基礎

目次
〇講義録の発刊にあたって
〇講師プロフィール
〇読者へのメッセージ○講義録
- はじめに
- 第1章 労働法の全体像と労働組合法の基礎
- Ⅰ 労働法の全体像を理解する
- 1 なぜ労働法について学ばなければならないのか?
- 2 労働法はどのような法?
- 3 労働法の3つの領域~どのような方法で労働者をサポートするのか?
- 4 労働条件は何によって決まっているか?
- Ⅱ 労働組合の基本ルール
- 1 労働組合法の見取り図
- 2 組合を結成して活動する
- 3 団体交渉を行う
- 4 団交を受けて労働協約を取り決める
- 5 実力行動に出る:争議行為
- 6 労働組合の権利を守る:不当労働行為制度
- Ⅰ 労働法の全体像を理解する
- 第2章 労働契約の基礎
- Ⅰ 労働契約の基本構造
- 1 労働契約の定義:労契6条
- 2 労働契約の契約類型としての特徴と関連テーマ
- 3 労働契約の一方当事者である「労働者」とは?
- Ⅱ 使用者の指揮命令権とその行使の限界~転勤(配転)命令を素材に
- 1 基本となる判断枠組み
- 2 どのような場合に転勤命令権があるといえるか?
- 3 どのような転勤命令権の行使が濫用的と判断されるか?
- Ⅲ 使用者が労働者に賃金を支払わなければならない場合とは?
- 1 労働契約に定められた労務が提供されれば常に賃金支払いが必要?
- 2 使用者が指示した業務でなければ、賃金をもらえないのか?
- Ⅳ 合意による労働条件の不利益変更が認められるためには?
- 1 合意の成立の仕方と論点の所在
- 2 他の労働条件決定方法との関係
- 3 合意の認定ルール
- 4 労働契約に付随する義務~特に合意しなくても生じる義務
- Ⅰ 労働契約の基本構造
- 第3章 労働基準規制と非正規雇用規制
- Ⅰ 賃金
- 1 賃金保護の構造
- 2 労基法上の賃金保護
- 3 賞与・退職金
- Ⅱ 労働時間・休息・休日
- 1 労働時間規制の目的と枠組み
- 2 原則となる労働時間規制
- 3 原則を修正する制度
- 4 年次有給休暇
- Ⅲ 非正規労働(パート・有期)に対する法的規制
- 1 なぜ「問題」になるのか?
- 2 共通規制
- 3 有期労働に対する規制
- Ⅰ 賃金
ご注文
-
No.28 歴史からみた労働組合の役割

目次
○講義録の発刊にあたって
○講師プロフィール
○読者へのメッセージ○講義録
- はじめに
- 第1講 先駆者の苦闘と歴史の教訓
- 1.序言
- 2.第一期組織化運動
- 3.第二期組織化運動
- 4.社会改革思想の実験場
- 5.西尾末廣
- 6.組織化の限界
- 7.労働組合法をめぐる攻防
- 9.渋沢栄一の教訓
- 10.残された成果
- ※「8.海員組合の教訓」については講義で触れていないため講義録には記載していません
- 第2講 戦後労働運動の展開
- 1.燎原の火:戦後改革と急激な組織化
- 2.組合結成(その1)石井鐵工所蒲田工場従業員組合
- 3.組合結成(その2)小泉製麻労働組合
- 4.組合結成(その3)東京重機従業員組合
- 5.組合結成(その4)日清紡労働組合
- 6.組合結成(その5)宇部窒素労働組合
- 7.戦後直後期の運動1:完全雇用闘争
- 8.戦後直後期の運動2:インフレ下の賃金闘争
- 9.占領政策転換と産別会議の壊滅
- 10.総評結成と労働運動の再建
- 11.雇用安定を求めて:解雇争議
- 12.春闘と賃金決定システムの形成
- 第3講 労働戦線の分裂と統一
- 1.統一から分裂へ
- 2.総評民間の勢力後退
- 3.IMF-JCの結成と展開
- 4.石油危機のインパクト
- 5.行政改革と官公労の行動変化
- 6.統一運動第1期:22 単産会議の失敗
- 7.統一運動第2期:政推会議と全民労協
- 8.統一運動第3期:民間連合と連合
〇講義レジュメ
ご注文
-
No.27 仕事と賃金

目次
○講義録の発刊にあたって
○講師プロフィール
○読者へのメッセージ○講義録
本講義では、講義レジュメのうち、結論にあたる「5.『働き方改革』と労使関係の課題」から説明し、その後、「1.労使関係の方法」から順に話したため、目次も説明順としていますはじめに
- 5.「働き方改革」と労使関係の課題
- 5-1.「働き方改革」の本質
- 5-2.「働き方改革」の新しさ
- 5-3.「働き方改革」に向けての基本的視点
- 5-4.雇用関係改革の課題
- 5-5.労使当事者の課題
- 1.労使関係の方法
- 1-1.方法の伝統
- 1-2.ルールによる労使関係制度の国際比較
- 2.賃金のルール
- 2-1.外国の調査から(生産労働者)
- 2-2.外国の調査から(ホワイトカラー)
- 2-3.日本の賃金
- 2-4.論点
- 3.仕事のルール:自動車産業の調査から
- 3-1.トヨタの場合
- 3-2.GMの調査から
- 3-3.フォルクスワーゲン調査から
- 4.仕事のルールと賃金のルールの統一的理解=労使関係
- 4-1.仕事のルール・賃金のルールの関係=可視化
- 4-2.仕事管理・報酬管理・雇用関係の欧米と日本の体系的理解
- グループワーク
〇講義レジュメ
ご注文
- 5.「働き方改革」と労使関係の課題
-
No.26 「安心社会」への戦略を考える

目次
○講義録の発刊にあたって
○講師プロフィール
○読者へのメッセージ○講義録
はじめに- Ⅰ.今、日本社会に広がる不安の背景は何だろう?
- 1・1 コロナ禍が浮き彫りにした日本社会の脆弱さ
- 1・2 高齢世代の不安
- 1・3 現役世代の不安
- 1・4 社会保障支出増大でも貧困率増大
- 2.これまで日本社会は、社会保障にそれほどお金を使わなかったのに貧困や格差が今日ほど顕著ではなかったのはなぜであろうか?
- 2・1 これまでの日本型生活保障
- 2・2 日本型生活保障の解体
- 3.連合の「働くことを軸とする安心社会」とはどのような社会のビジョンか?
- 3・1 いかなるビジョンか?
- 3・2 5つの橋とは何か
- 4.活力ある安心社会へ橋をどう架けていくか 討議テーマ
〇講義レジュメ
ご注文
- Ⅰ.今、日本社会に広がる不安の背景は何だろう?
-
No.25 日本の財政と社会政策の課題

目次
○講義録の発刊にあたって
○講師プロフィール
○読者へのメッセージ○講義録
はじめに- Ⅰ.日本における不平等拡大の現状と背景について
- 1.不平等レジームの多様性
- (1)経済学における不平等研究
- (2)戦争の影響による平等化、労働組合の役割
- (3)歴史的パースペクティブからみた不平等の現状
- (4)日本の経済的不平等が小さく見えてしまう理由
- (5)日本における経済的不平等拡大の背景と特徴
- (6)貧困層の拡大と産業競争力の喪失
- 2.日本型生活保障システムの特徴
- (1)日本は「自己責任社会」
- (2)極めて小さい所得再分配政策の効果
- (3)現役層に対する所得保障制度
- (4)公的社会保障の規模は大きいのか
- (5)社会保険料と世代間再分配
- (6)社会保険料と所得税との関係
- (7)貧困を拡大させる日本型社会保障システム
- 3.コスト抜きの問題解決は可能か?
- (1)国際比較からみる日本の政府債務残高の水準
- (2)量的・質的緩和政策のカラクリ
- (3)企業の内部留保と家計貯蓄との関係
- (4)財政赤字の持続可能性
- 4.税について考える
- (1)税・社会保険・国債のアンバランス
- (2)低い税負担にも関わらず税に不満を抱く日本人
- (3)税・社会保険・国債を比較する
- 5.普遍主義と財政
- (1)政府に対する信頼を生むためには給付の普遍性が必要
- (2)給付においては貧しい者も富める者も対等に扱うことで格差は縮小
- 6.消費税を考える
- (1)~ディスカッション~
- (2)解説~消費税の使途~
- (3)解説~各種税金の性質とその違い~
- 1.不平等レジームの多様性
ご注文
- Ⅰ.日本における不平等拡大の現状と背景について
-
No.24 国際労働運動の課題と対応
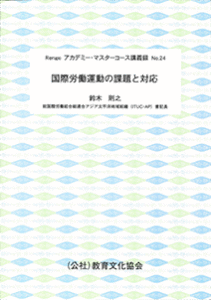
目次
○講義録の発刊にあたって
○講師プロフィール
○読者へのメッセージ○講義録
はじめに- Ⅰ.国際労働運動の原則
- (1)キーワード
- (2)中核的労働基準
- (3)全繊・ゼンセン同盟(現UAゼンセン)での取り組みの事例
- Ⅱ.アジアの労働の現状
- (1)縫製工場ビルの倒壊
- (2)インフォーマルセクター(家内労働)
- (3)フィールドでの児童労働
- (4)工場内での児童労働
- Ⅲ.経済指標等からみる労働の現状
- (1)世界のGDPの国別配分状況
- (2)富の偏在
- (3)生活水準指標の分布
- (4)労働分配率の低下
- (5)雇用構造の変化
- (6)正規・非正規間の賃金格差
- (7)労働組合組織率の現状
- (8)労働生産性と賃金のかい離
- (9)ITUCの労働基本権指標
- (10)格差の拡大
- Ⅳ.組織活動について
- (1)各国の労働組合組織について
- (2)国際労働運動の組織
- (3)キャンペーン活動
- (4)労働協約の適用による格差縮小
- (5)GDPに占める社会保障費
- (6)累進税による格差縮小
- (7)男女平等の促進~女性労働運動の強化
- (8)青年運動の活性化
- (9)政治的パワーの示威
- (10)アフガニスタンでの事例
- (11)ミャンマーでの事例
- Ⅴ.政策実現に向けた取り組み
- (1)国際労働政策のプラットフォーム
- (2)各国首脳への政策提言
- (3)国際レベルの政策協議の事例
- (4)ILOでの取り組み
- Ⅵ.グループワーク
- (1)テーマ発表
- (2)各ゼミからの発表
- (3)講師からの講評
- Ⅶ.ITUC-APでの組織運動について
- Ⅷ.まとめ
- (1)国際労働運動とは何か
- (2)国際労働運動の原理
- (3)連合の役割
- (4)世界人権宣言
- (5)政治的パワーをどう創り出すか~ネパールの事例から
- Ⅵ.おわりに
ご注文
- Ⅰ.国際労働運動の原則
-
No.23 現代日本経済論

目次
○講義録の発刊にあたって
○講師プロフィール
○読者へのメッセージ
○講義録
- はじめに
- Ⅰ.日本の経済社会をみる眼
- (1)いま問われるこれからの経済社会構想
- (2)歴史的文脈の把握
- ①安定していた19世紀システム
- ②二度の世界大戦と大恐慌による大転換
- ③第二次世界大戦後の福祉国家体制
- ④福祉国家体制の行き詰まりと新自由主義
- ⑤新自由主義の行き詰まりと新たな社会経済構想の模索
- Ⅱ.日本経済への基本視座
- (1)経済とは?経済の基本問題とは?
- (2)経済(景気)は循環運動する
- (3)日本経済をマクロ的に把握する
- (4)日本経済の発展段階について
- Ⅲ.改めて経済活動のグローバリゼーションとは?
- (1)グローバル化の歴史的経緯
- (2)グローバリゼーションの論理
- (3)グローバリゼーションの歴史的意味
- Ⅳ.日本型ビジネスモデルの変化
- (1)フルセット型産業構造の解体
- (2)ビジネスモデルの変化
- ①垂直統合モデルと水平展開モデル
- ②生産方式(技術)の変化
- ③企業の海外進出が活発化する中での産業空洞化問題
- Ⅴ.経済と社会の関係について
- (1)福祉国家体制の行き詰まり
- (2)経済と社会
- ①ロバート・パットナムの所説によりながら
- ②アマティア・センの所説によりながら
- (3)新しい経済社会をつくる
ご注文
-
No.22 労働法の基礎

目次
○講義録の発刊にあたって
○講師プロフィール
○読者へのメッセージ
○講義録
- はじめに
- 【第1部】労働法総論と労働組合法
- Ⅰ.伝統的な労働法理論と労働法制
- Ⅱ.労働法の法源
- Ⅲ.労働法の基本理念の見直し日本型雇用社会の変容
- Ⅳ.労働法の現代的課題
- Ⅴ.労働組合法
- 1.憲法28条による労働基本権保障と労働組合法制
- 2.労働組合
- (1)労働組合法上の労働組合
- ①労働組合法上の労働者とは
- ②労働組合の自主性
- ③労働組合の民主制
- (2)ユニオン・ショップ協定の効力と相対性
- 3.不当労働行為制度
- (1)不当労働行為制度の特徴と原状回復主義
- (2)不当労働行為の救済手続き
- (3)不当労働行為の4つの類型
- 4.団体交渉
- (1)団体交渉の当事者と交渉担当者
- (2)団体交渉の対象―義務的交渉事項
- (3)団体交渉の様態―誠実交渉義務
- 5.労働協約
- (1)労働協約の成立要件
- (2)労働協約の規範的効力
- (3)協約の規範的効力と労働条件の不利益変更
- (4)労働協約の不利益変更の限界
- (5)労働協約の一般的拘束力と不利益変更
- 6.団体行動
- (1)組合活動
- (2)争議行為
- 【第2部】労働基準法
- Ⅰ.労働法制における労基法の位置と特徴
- Ⅱ.労働基準法の適用範囲―労基法上の「労働者」
- Ⅲ.労基法上の賃金規制
- 1.労基法上の賃金とは
- 2.賃金支払いの規制―賃金支払いの4原則
- (1)通貨払いの原則
- (2)直接払いの原則
- (3)全額払いの原則
- (4)毎月一回・一定期日払いの原則
- 3.休業手当
- 4.成果主義的賃金制度と使用者の公正(適正)評価義務
- Ⅳ.労基法上の労働時間規制
- 1.労働時間の実情と労働時間政策の変化
- 2.法定労働時間の原則
- 3.時間外・休日労働の法的規制
- 4.時間外・休日労働義務
- 5.労働時間の弾力化
- (1)1カ月単位の変形労働時間制と1年単位の変形労働時間制
- (2)フレックスタイム制
- 6.労働時間のみなし制
- (1)事業場外労働のみなし制
- (2)裁量労働制のみなし時間
- 7.労働時間規制の適用除外
- 8.高度プロフェッショナル制度の導入議論
- 9.年次有給休暇
- 【第3部】労働契約法
- Ⅰ.労働契約法とは
- Ⅱ.労働契約の終了
- 1.解雇の法的規制
- 2.解雇の客観的合理的理由と社会通念上の相当性
- 3.整理解雇の法理
- Ⅲ.労働契約の締結
- 1.労働条件の明示義務
- 2.採用内定と試用期間
- (1)採用内定の法的性質と内定取消
- (2)試用期間と本採用の拒否
- Ⅳ.労働契約の期間
- 1.労働契約の期間の最長限度規制
- 2.有期労働契約の更新拒絶の法理と2012年改正労働契約法
- (1)有期労働契約の更新拒絶の法理
- (2)有期労働契約の無期労働契約への転換
- 3.有期労働契約であることによる不合理な労働条件の禁止
- Ⅴ.就業規則による労働条件の決定と変更
- 1.就業規則の機能と労基法の規制
- 2.就業規則の最低基準効
- 3.就業規則の法的性質―労働契約規律効
- (1)就業規則の法的性質
- (2)秋北バス事件最高裁判決と2007年労働契約法7条
- 4.就業規則の労働条件の不利益変更と労働契約法10条
- (1)就業規則の不利益変更と最高判決
- ①就業規則の不利益変更をめぐる問題の難しさ
- ②最高裁の合理性判断枠組み
- ③労契法10条による立法的決着
- Ⅵ.労働契約上の権利・義務―配転・出向をめぐる問題
- 1.個別的労働条件の決定と変更―配転・出向をめぐる法的問題
- 2.配転の法的根拠と権利濫用
- (1)配転命令の法的根拠
- (2)配転命令権の濫用
- 3.出向の法的根拠と権利濫用
資料:判例集
ご注文
-
No.21 ジェンダーと労働

目次
○講義録の発刊にあたって
○講師プロフィール
○読者へのメッセージ
○講義録
- はじめに
- 【第1部】フェミニズム運動とジェンダー
- I.フェミニズム運動
- 1.男女同権運動からフェミニズム運動へ
- 2.私的世界と公的世界
- II.「ジェンダー」という言葉とジェンダーの視点
- 1.文化的社会的に作られた性別と生物学的な性別
- 2.公私二元論に対する挑戦
- I.フェミニズム運動
- 【第2部】女性差別撤廃条約と日本政府
- I.女性差別撤廃条約採択に至るまで
- II.女性差別撤廃条約の考え方と日本政府が批准するための課題
- 1.女性差別撤廃条約の考え方
- 2.批准するための3つの課題
- 【第3部】日本の女性労働と女性労働法制の現状と課題
- I.均等法制定において何が議論されたのか
- II.均等法はどのような仕組みか
- III.女性労働をめぐる法制度
- 1.法制度の全体構造
- 2.男女雇用機会均等法
- (1)法的効力
- (2)性差別
- (3)間接差別
- (4)不利益取扱い
- 3.育児・介護休業法
- IV.均等法施行30年目の女性労働の現状
- V.日本の法制度の問題
- 1.均等法の課題
- 2.新しい立法の動き
- おわりに
- 質疑応答
○講義資料
1.講義レジュメご注文
-
No.20 現代社会保障のとらえ方

目次
○講義録の発刊にあたって
○講師プロフィール
○読者へのメッセージ
○講義録
- はじめに
- 【第1部】
- I.社会保障の体系
- 1.社会保障の3つの系譜
- 2.社会保障の分類方法
- 3.社会保険とは
- 4.社会保険の三類型
- 5.日本の社会保障制度の大分類
- I.社会保障の体系
- 【第2部】
- II.健康保険
- 1.「国民皆保険」の採用
- 2.医療保険制度の概要
- 3.被保険者とその決定の順序
- 4.家族(被扶養者)の扱い
- 5.高額療養費制度
- 6.現金給付
- 7.保険者の財政状況
- 8.国民医療費の動向と国際比較
- II.健康保険
- 質疑応答
- III.介護保険
- 1.保険者と被保険者
- 2.財源構成
- 3.保険給付と保険料
- 4.介護保険財政の見通し
- III.介護保険
- 【第3部】
- IV.年金
- 1.日本の公的年金制度概観
- 2.国民年金
- 3.被用者年金(厚生年金、共済組合)の拠出と給付
- 4.年金給付の調整
- 5.年金財政の見通し
- 6.年金の財政方式
- V.雇用保険
- IV.年金
- デンマークの雇用政策・労使関係
- 参考文献紹介
- おわりに
ご注文
-
No.19 労働運動の歴史

目次
○講義録の発刊にあたって
○講師プロフィール
○読者へのメッセージ
○講義録
【前編】
- はじめに
- 1.講義の目的
- 2.労働者にとっての幸せ、国民にとっての生活資源とは
- 3.参考文献紹介
- 序章 労働運動とはなにか
- 1.労働運動とは、労働者の願望を実現するための労働者の集団的活動
- 2.労働組合成立以前から存在した労働運動
- 3.現代にいたるまでの労働運動の多様なかたち
- 4.社会運動としての労働運動
- 第1章 労働組合の成立と発展
- 1.イギリスの1760年代~初期の労働組合
- 2.団結禁止法とその廃止
- 3.労働組合の新たな発展(1830年代)
- 4.クラフトユニオン
- 5.産業別一般組合の形成
- 6.ILO(国際労働機関)の成立と展開
- 7.ロシア革命とその影響 ~第一次世界大戦のもう1つの結果
- 8.ニューディールとアメリカ労働組合
- 9.冷戦と国際労働運動
- 10.福祉国家を推進する労働組合
- 11.新自由主義体制下で苦闘する労働組合
- 第2章 第二次世界大戦までの日本の労働組合
- 1.労働組合期成会(1897年)
- 2.初期の3つの労働組合(1897年、98年)
- 3.治安警察法~労働組合死刑法
- 4.関心は社会主義運動へ
- 5.幸徳・田添論争
- 6.友愛会の成立と総同盟への発展(1912年~)
- 7.分裂の歴史
- 8.戦前の3大争議
- 9.労働組合と工場委員会
- 10.戦前期の労働戦線統一
- 11.産業報国運動
【後編】
- 第3章 敗戦直後から1955年まで
- 1.巨象のような労働組合統一ならず
- 2.5大改革指令(1945年)
- 3.生産管理とストライキ(1945~46年)
- 4.総同盟と産別会議(1946年)
- 5.2.1ゼネストの挫折(1947年)
- 6.片山内閣(1947年)
- 7.民同派の結成と発展(1947~48年)
- 8.マッカーサー書簡から定員法へ(1948~49年)
- 9.総評の結成(1950年)
- 10.にわとりからあひるへ(1951年~)
- 11.電産・炭労ストと労闘スト(1952年)
- 12.4単産批判から全労会議結成へ(1954年)
- 13.総評高野事務局長批判の高まり
- 第4章 高度経済成長期の労働組合
- 1.春闘の開始(1955年)
- 2.社会党の統一(1955年)
- 3.中立労連の結成(1956年)
- 4.勤評、警職法反対闘争、そして安保闘争(1957~60年)
- 5.三池闘争、炭労政策転換闘争(1960~62年)
- 6.4.17公労協ストと共産党4.8声明(1964年)
- 7.池田・太田会談(1964年)
- 8.IMF-JCの結成(1964~66年)
- 9.日韓、ベトナム反戦、沖縄返還、70年安保、公害反対闘争(1960年代後半)
- 10.国鉄マル生争議(1969~70年)
- 11.生活闘争(1970年)
- 12.オイルショックと労働組合(1974年)
- 13.スト権ストの敗北
- 第5章 労働戦線統一への道
- 1.2度にわたる宝樹論文
- 2.統一労組懇
- 3.連合結成にいたるまで
- 終章 連合24年、労働戦線統一の成果は達成されたか
○講義資料
ご注文
- はじめに
-
No.18 経済の見方

目次
○講義録の発刊にあたって
○講師プロフィール
○読者へのメッセージ
○講義録
- はじめに(講義概要)
- I 世界における日本の経済情勢
- 1.欧米より余力のある日本の経済情勢
- 2.マスメディアの煽動と実体
- 3.アメリカンスタンダードのルールによる束縛
- 4.小泉・竹中路線と変わらない橋下維新
- 5.海外直接投資がまねく弊害
- II 賃金・物価の決まり方
- 1.インフレが起きるメカニズム その1
- 2.インフレが起きるメカニズム その2
- 3.失業によって下がる生産性
- 4.デフレは起きていない
- III 日本の企業のあるべき姿
- 1.企業は誰のものか
- 2.「人的資本」と「物的資本」
- 3.市場に置き換えられていく企業
- 4.日本型企業の利点
- 5.「市場型」企業と「成長型」企業
- 6.企業成長と経営権のコンフリクト
- IV 今後の日本の課題(まとめ)
- 1.信義を通す
- 2.1人当たりGDPを基準にする
- 3.他国に依存しない
- 4.アメリカ経済の衰退と日本の転機
○講義資料
ご注文
-
No.17 国際労働運動の課題と連合の対応

目次
○講義録の発刊にあたって
○講師プロフィール
○読者へのメッセージ
○講義録
- はじめに
- I グローバル化された社会の中での労働組合の役割を考える
- 1.国際労働組合運動の組織概要
- 2.国際労働組合運動の課題「ITUCの活動方針」
- 3.持続可能な経済、社会、環境の追求
- 4.世界経済危機と雇用問題、その克服
- 5.ディーセント・ワークと企業の社会的責任(CSR)
- 6.グローバル枠組み協定(GFA)の締結にむけて
- II ILO(国際労働機関)の理解と活用のために
- 1.ILOの目的・目標と基本文書
- 2.国際労働基準の採択と適用
- 3.ILOのグローバル化への対応:ディーセント・ワークの実現にむけて
- 4.ディーセント・ワーク実現への行動
○講義資料
ご注文
-
No.16 労働法の基礎 ※ 在庫なし

目次
○講義録の発刊にあたって
○講師のプロフィール
○読者へのメッセージ
○講義録
- Ⅰ 労働法が労使関係を支配する
- Ⅱ 労働法の基本構造と就業規則
- Ⅲ 労働組合をめぐる法律問題
○講義資料
-
No.15 組合機能の点検と改革 ※ 在庫なし

目次
○講義録の発刊にあたって
○講師の略歴
○読者へのメッセージ
○講義録
- はじめに
- 1.労働組合とは
- 2.日本の労働組合の特徴
- 3.戦後型年功賃金から能力主義賃金へ
- 「年の功」から「年と功」へ-
- 4.「成果主義」への展開-1990年代の賃金改革-
- 5.非正規従業員の増大と組織化
- 6.今日の労働組合に期待される機能と課題
○講義資料
-
No.14 国際比較から見た日本の労使関係 ※ 在庫なし

目次
○講義録の発刊にあたって
○講師の略歴
読者へのメッセージ○講義録
- はじめに
- 1.比較と歴史の視点
- 2.労働運動と労使関係の歴史
- 3.国際比較 -労働組合と社会-
- 4.日本の労使関係
- 5.それでも大きな世界の流れ。世界に目を向けよう。
○グループワーク討議
○講義資料
-
No.13 ジェンダー論 ※ 在庫なし

目次
○講義録の発刊にあたって
○講師の略歴
読者へのメッセージ○講義録
- はじめに
- 1.ジェンダーという視点
- (1)生物学的性差、社会的・文化的規範、社会生活領域の棲み分け
- (2)二分法的な「知」のあり方
- 2.ウィーン・フィルの「女人禁制問題」(’96)
- (1)女性が舞台へ上がれない理由
- (2)舞台へ上がる女性が出始める
- 3.ジェンダーをめぐる情勢
- (1)学術世界・ 大学教育でのジェンダーの定着
- (2)ジェンダーとは何か
- 4.日本のジェンダー関係の特質
- 5.女性の社会的地位としての帰結
- 6.ジェンダー関係の強固さ・産業化と性別分業家族モデル
- ◆◇◆ グループごとの討議 ◆◇◆
- 7.日本における雇用慣行の変動とジェンダー関係
- (1)1990年代以降のトレンド~企業サイド
- (2)1990年代以降のトレンド~女性労働をめぐる政策の変化
- 8.職場の変容:女性活用・任用へのとりくみ:総合スーパーマーケットX社の事例
- (1)男性によるマネジメントの独占
- (2)生活者の視点
- (3)女性主任の登用
- (4)女性店長作り
- (5)女性店長の2つのキャリア類型
- (6)ボトムアップの効用
- (7)再生産と変容の側面
- (8)ジェンダー平等実現のための企業と労働組合
- (9)トップの決断
- (10)ジェンダーという「知」 を活かす視点
- (11)大切なこと~Opportunity Now 「機会を、今や」~
○グループごとによる質疑・討論
-
No.12 現代政治学講座-21世紀の政治政策課題への対応
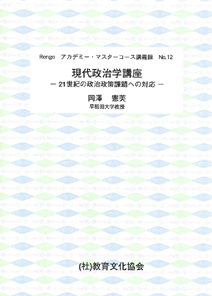
目次
○発刊にあたって
○講師プロフィール
○読者へのメッセージ
○講義録
- はじめに-いつも地球儀を近くに置いて
- 1.リーダーとしての発想の出発点~地球規模でモノを考える
- 地球儀を転がしてみると・・・
- 「“約”208の国と地方」の意味
- 不透明感と不確実性、相互依存度が高まる中で・・・
- 2.変化と変動の時代、常識と非常識は時とともに簡単に反転する-結論1
- 昨日の常識は今日の非常識、今日の非常識は明日の常識に
- 組合リーダーは前例踏襲主義と横並びに埋没していないか
- ~「連合」は最先端の知識・常識・情報の集積を
- 3.変化と変動の時代、常識と非常識は空間とともに簡単に反転する-結論2
- 「自分たちの常識は世界の常識」と思い込んではいないか
- 4.もっと意思決定過程を多様化せよ:価値複合的な意思決定構造を-結論3
- 「松坂60億、ホークス50億」:グローバル人事行政の足音
- “ダイバーシティ・マネジメント”~「開け、開け、もっと開け」
- ある自治体の住民投票の例~時代を切り拓く大胆な発想
- 「選挙権は20歳から」は世界の常識か?
- 異文化コミュニケーションを可能にし
- グローバリゼーション・国際化に敏感な組織運営を目指そう
- 5.リーダーシップのスタイルは変化する
- 「リーダー」と「フォロワー」の関係に作用する変数
- ~「コーポレート・カルチャー」と「コーポレート・リソース」を見つめ直す
- 6.少子高齢社会がもたらすインパクト
- 日本を直撃する高齢化のスケール
- 「合計特殊出生率1.25」~ウルトラ級の少子化が日本社会を根底から変える
- 墓地は、不動産は、家業は、介護はどうする?
- ~「長男・長女社会」の進行がもたらすもの
- 政策対応の遅れのツケが「働く女性」の肩にのしかかる
- 労働組合の対応はどうだったのか
- 7.ライフスタイルの「多様化」とは~15の構成要素
- 福祉を優先するなら増税を恐れるな
- 8.「多様化」の要素とは何か
- 9.21世紀の福祉システムの前提~重すぎる5つの与件
- 10.少子・高齢化時代の福祉システムの構想
- ~《経済大国の論理》から《生活大国の論理》へ
- 何よりも「不安感を取り除く」ことが重要
- 「不安感を取り除く」ために~働く仲間の連帯で社会財を作ろう
- 労働力人口、納税人口を調達する方法は
- 自分たちの既得権をどう考えるか~もっと多様で「開かれた」組織へ
- 「日本型経営組織論」の実態は~既にその前提条件は崩れている
- 「発展・開発と安心・安全」「成長と福祉」をどうバランスさせていくか
- 11.「連合」にこそ長期ビジョンを描いてほしい
- ~そのためにも多様な仲間を受け入れ、組織率を上げるしかない
- さいごに-やり甲斐のある時代~顕微鏡と望遠鏡、心にいつも地球儀を持って
○講義資料
ご注文
-
No.11 日本経済とグローバリゼーション

目次
○発刊にあたって
○講師プロフィール
読者へのメッセージ○講義録
- はじめに
- 第1章 産業・企業のグローバリゼーション
- 第1節 グローバリゼーションに至る歴史的推移
- 第2節 具体的な事例によるグローバリゼーションの検証
- 第3節 グローバリゼーションの論理
- 第4節 グローバリゼーションが持つ歴史的含意
- 第5節 直接投資についての補足説明
- 第2章 産業の空洞化をめぐって
- 第1節 産業の空洞化とは
- 第2節 日本型生産システムの強さの喪失
- 第3節 付加価値の源泉の移転
- 第4節 改めて産業の空洞化とは
○質疑応答
ご注文
-
No.10 現代経済・社会論-現代社会における労働組合の役割 ※ 在庫なし

目次
○発刊にあたって
○講師プロフィール
読者へのメッセージ○講義録
- はじめに
- 1.現代経済と社会進歩を考える
- 2.長期経済停滞期以降の労使関係の展開過程と課題
- (1)「職場の代表機能」と「社会の代表機能」
- 3.日本型労使関係モデルとその未来
- (1)コーポレート・ガバナンスと産業民主主義
- (2)日本における企業統治の成立と変容の可能性
- (3)日本型労使関係と日本型コーポレート・ガバナンス成立の背景
- (4)日本型雇用システムヘの新たな試練
- (5)労働条件決定のあり方を考える-春闘とその特質
- (6)春闘方式-日本の賃金決定における「二重の奇跡」
- (7)総合労働条件交渉の新たな課題
- 4.現代の「くらし・仕事」の状態を直視して、社会像・労働像を考える
- (1)「杜会の持続可能性」-「ワーク・ライフ・バランス」の視点
- (2)私達のめざす社会像とは?
- (3)連合と社会改革モデルをめぐる検討
- (4)連合のめざす社会モデル-「労働を中心とする福祉型社会」
- 5.労働組合の「力」とは?-5つの力
- むすび
-
No.9 経済・社会の変動と社会保障の課題 ※ 在庫なし

目次
○発刊にあたって
○講師プロフィール
読者へのメッセージ○講義録
- はじめに
- 第1章 社会保障の横断的な視点
- 第1節 基本的な考え方
- 第2節 大きな政府論対小さな政府論の克服
- 第3節 社会保障改革の流れ
- 第4節 事業主負担の謝った議論
- 第2章 2004年年金改革の影響と評価
- 第1節 2004年年金改革の効果
- 第2節 2004年年金改革の意義
- 第3節 マクロ経済スライド方式の意味
- 第3章 最低所得保障の構築
- 第1節 年金一元化を巡る経緯と問題点
- 第2節 生活保護の問題点
- 第3節 最低保障政策
- 第4章 医療保険・介護保険改革
- 第1節 自己負担による需要抑制の限界
- 第2節 診療報酬体系の見直し
- 第3節 医療保険改革を巡る2つのテーマ
- 第4節 高齢者医療保障の課題
- 第5章 社会保障体系の見直し
- 第1節 50%ルールの再検討
- 第2節 社会保障の役割
- 第3節 21世紀型社会保障
- 第1章 社会保障の横断的な視点
- おわりに;若干の補足
- 質疑応答
- はじめに
-
No.8 労働法制の課題 ※ 在庫なし

目次
○発刊にあたって
○講師プロフィール
読者へのメッセージ○講義録
- はじめに ~労働法の概要
- 第1章 雇用法制
- 1.日本の雇用に関する法制・法理の概要と特色
- (1)解雇に関する法的規制の概要
- (2)解雇権濫用法理
- (3)最近の動向
- 2.労働基準法による解雇ルールの法制化
- (1)立法化過程における論点と問題点
- 1.日本の雇用に関する法制・法理の概要と特色
- 第2章 非典型雇用
- 1.有期労働契約法制
- (1)有期契約に関する労働法の規制とその緩和
- (2)有期契約と雇用ルール
- 2.パートタイム労働法制
- (1)日本におけるパートタイム労働の特質と問題の所在
- 1.有期労働契約法制
- 第3章 企業組織変動と労働者保護政策
- 1.会社分割法制と労働契約承継法
- (1)会社分割の意義、形態、特徴
- (2)労働契約の承継
- (3)労働協約の承継
- (4)分割承継に関する労働者・労働組合の関与
- 2.営業譲渡をめぐる問題
- 3.企業倒産と労働者の保護
- 1.会社分割法制と労働契約承継法
-
No.7 組合経営 ※ 在庫なし

目次
○発刊にあたって
○講師プロフィール
読者へのメッセージ○講義録
- はじめに
- 「組合経営」とは
- 労働運動の目的 -ピープル・ファースト-
- 新時代におけ労働組合の経営資源
- 大衆民主主義から代表民主主義へ
- 労働組合における人材育成の必要性
- 情報化時代の労働組合経営
- 再び大衆民主主義から代表民主主義へ
- 個人と社会のかかわり
- 労働組合のリーダー像
- プロフェッショナルとしての3つの力
- 情報の選別と活用
- 労働組合の経営資源の再考を
- 企業経営と組合経営の違い -4つのM-
- グループ討議の発表
- グループ討議のまとめ
- 労使関係四つの原則
- 労働組合の総合力
- 絡み合いながら広がる労働運動
- それぞれの組合の機能と役割
- 組合員一人一人が参加することが原点
- ボランティア・ユニオニズムへの発展
- 労働組合の役割と機能の分析を
- 21世紀は「多様性」と「二極化」の社会
- 真価が問われる21世紀の労働組合 -ミニマム重視の労働組合へ-
- 新しい労働運動の視点 -8つのSと4つのC-
- ウィンストン・チャーチルの言葉 -むすびにかえて-
-
No.6 グローバル経済下の企業戦略

目次
○発刊にあたって
○講師プロフィール
読者へのメッセージ○講義録
- はじめに ─ 企業戦略の概要と労働組合の変革への応用
- 1.革新のポイント
- 2.ビジネスの新原則
- 3.ソフトウェアを加味したビジネス ─ 無形資産の価値
- 4.パラダイム論について
- 5.リーダーのスキルと志
- 6.マネージャー(上司)の新しい役割の3要素
- 7.リーダーのスキル
- 8.まとめ
ご注文
-
No.5 ジェンダー論-男性の働き方を見直す- ※ 在庫なし
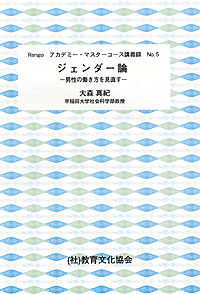
目次
○発刊にあたって
○講師プロフィール
読者へのメッセージ○講義録
- (1)ジェンダー論の意義
- ジェンダーの視点
- 女性の問題という誤解
- 女性の多様性
- 男性への問い直し
- (2)労働におけるジェンダー
- 事実と認識のずれ
- あいまいな性別の境界
- ペイド・ワークとアンペイド・ワーク
- 男性の働き方の見直し
- 女性のM字型就労
- コンパラブル・ワース
- (3)雇用形態とジェンダー
- 女性に偏る非正規雇用
- 女性自身のパート選択
- 性別役割分業の強化
- 性別格差別を生む雇用形態
- (4)均等待遇原則の確立
- 正規雇用と非正規雇用の格差
- セクシャル・ハラスメント
- 雇用関係の空洞化 -派遣・請負・SOHO-
むすび
グループ討議○講義資料
- (1)ジェンダー論の意義
-
No.4 少子・高齢社会の暮らしの設計

目次
発刊にあたって
講師プロフィール
読者へのメッセージ○2001年度講義録(2001年11月15日講義)
高齢化と社会保障・社会福祉-オランダの事例を中心に- はじめに
- 1.オランダの福祉国家の特徴
- 2.オランダの高齢労働者の就労と引退
- 3.オランダの医療・介護保障
- 4.地域福祉の展開
- 5.オランダの福祉国家から学ぶもの-まとめにかえて-
グループディスカッション
全体討論
○2002年度講義録(2002年11月14日講義)
女性就労の高まりと子育て支援策-オランダの事例を中心に- はじめに
- 1.福祉国家の類型論と女性就労の状況
- 2.オランダで女性の職場進出が遅れた主な理由
- 3.男女平等策と子育て支援策
- 4.最近のEUにおける「就労と社会的責任の両立支援策」
- 5.オランダにおける就労と子育て支援策
- おわりに
グループディスカッション(要旨)
全体討論
ご注文
-
No.3 組織拡大の事例研究

目次
発刊にあたって
講師プロフィール
議事録
- ●組織拡大-なぜ、どうやって
- -東京大学社会科学研究所教授 中村 圭介
- ●「組織づくり・アクションプラン21」の意味するもの
- -連合組織拡大センター総合局長 高橋 均
- ●組織拡大の実践(要約)
- -連合東京 鈴木 人司
- -連合埼玉 伊藤 彰久
- -連合大阪 丸田 満
講義資料
ご注文
- ●組織拡大-なぜ、どうやって
-
No.2 ジェンダー論 ※ 在庫なし

目次
発刊にあたって
講師プロフィール
読者へのメッセージ議事録
- 経済発展と女性の社会進出
- 経済学では賃金をどうみるのか
- 晩婚化や晩産化の動き
- 経済の発展にともなう女性の労働力率の変化
- 少子高齢化のインパクト
- パート労働者の増加はなぜおきているのか
- グループディスカッション
講義資料
-
No.1 労働運動の歴史 ※ 在庫なし

目次
発刊にあたって
講師プロフィール
読者へのメッセージ議事録
- 1.「労働運動史」とは何か
- 2.労働組合のはじまりと発展
- 3.日本の労働組合の発生と展開
- 4.戦前期日本の労働組合
- 5.敗戦と労働組合の興隆
- 6.労働4団体の時代
- 7.労働戦線統一の過程
- グループワーク討議
講義資料
労働組合運動史の略年表
参考資料1~10
